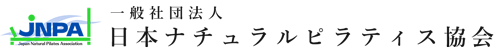なぜ健康経営?なぜピラティス?4070問題に備えて

ピラティス=健康経営?
2030年の4070問題に備えて
「社員の健康は大切」と口で言うだけでは、もはや時代遅れです。なぜなら、いまの時代、40代が“若手”とされる職場も増えています。あなたの会社はどうでしょうか?加えて、定年が70歳を超える時代は目の前に来ています。
あなたの会社は本当に社員を守れる準備ができていますか?
この記事では、私たちが、現在どのような問題を抱えて、またどのように解決していきたいのか?そのすべてを書いております。
1. 私たちが直面している3つの問題
1.1 高齢化する産業社会 - 40代が若者と言われる時代の到来
現代の日本において、産業社会の高齢化はますます進んでいます。多くの企業で「40代が若手」「50代中堅」とされる時代はすでに来ています。
ニュースを見みていても、次の3つの事がわかります。
現行の日本政府の取り組みを見る限り、...1.少子化対策には力を入れている、2.高齢者の社会保障を頑なに維持しようとする、3.中高年(40~64歳)の人材には手が回っていない...です。
現役の40~60代の対応が後回しになっているのです。対して、この世代は、2030年は日本の産業界を担う世代であり、最も人口が多いです。
論より証拠!
医療系調査機関のGemMedの人口調査によると、2030年からは50代後半の世代が働き盛りになります。
言い換えるなら、2025年の時点では50代社員は労働人口で最も多くなり、産業界の担い手になることは間違いないです。
2005年時点では、20代を現場で鍛え上げ、30代を主力に迎え、40代からは管理職を目指すことが常識でしたが、この人口分布を見てもおなじかん考えでいられるでしょうか?
1.2 人生100年時代 - 70歳超えが必然?
小泉進次郎氏の「高齢者でも働けばいい」という発言は、人生100年時代を迎えた日本における労働力不足への対応策として注目されました。少子高齢化が進む中、定年後も働き続けることが必要になるとされ、高齢者の労働力活用が不可欠だという背景がありました。しかし、この発言は「健康面を無視して高齢者に無理をさせる」と批判を受け、特に年齢を重ねると心身の健康が悪化しやすい現状を考慮すべきだという声が多く上がりました。
しかし、薄々と感ずいているように、人生100年時代という考え方は、単なる未来予測ではなく、実際のデータに基づく現実です。
日本における平均寿命は年々延びており、女性では約87歳、男性では約81歳に達しています。さらに、厚生労働省の調査では、2007年に生まれた子どもの半数が100歳以上まで生きるとされています。高齢者が70代、80代でも社会で活躍できる可能性が現実となってきています。
特に先進国において、引退年齢の延長や高齢者の再雇用制度が導入されていることから、100年時代に対応する社会の準備が進んでいます。
この「人生100年時代」における高齢化社会では、労働力不足を補うために高齢者の労働参加が不可欠です。しかし、年齢を重ねるとともに身体的・精神的な健康維持が難しくなるのは避けられません。したがって、70歳を超えても働くのは、当たり前の時代になるでしょう。
たとえ、政党が変わっても、この人口ピラミッドは変わることはないのです。
1.3 深刻な人材不足の時代へ
もしも、あなたがすでに出世を果たし、経営陣の一員となり「勝ち逃げできた」と思っていたら、大間違いです。
今後は、経営の一角を担うものとして、50~70代の社員を抱えることになります。彼らの健康やメンタルケアをサポートし、職場でのパフォーマンスを維持できる義務が伸し掛かります。これこそ本当の未曽有です。
もしかすると、あなたより年上の部下もいるかもしれません。年齢やキャリアの長さに関係なく、経営陣として、すべての社員が健康であり続けられる職場環境を提供する責任が重くのしかかるのです。
このような状況にも関わらず、日本で平均寿命は延びている一方で、健康寿命(健康で自立した生活を送れる期間)は十分に延びていないという現実があります。
- 平均寿命(厚生労働省「令和2年簡易生命表」より)
- 男性:81.64歳
- 女性:87.74歳
- 健康寿命(厚生労働省「令和3年版 健康寿命データ」より)
- 男性:72.68歳
- 女性:75.38歳
これにより、男性は約9年間、女性は約12年間、健康を損ねた状態で生活を余儀なくされます。それでも、日本を支えるために働かざるを得ない状態を強いられているのです。
これからの時代を担うのは、20~30代ではなく、40代~50代なのです。
よって、何としてでも健康寿命を20年...少なくとも10年はあげる必要はあると私は考えます。
2.ピラティスが注目される理由とは?
ピラティスは、高齢者やデスクワーク、肉体労働者にとって効果的なメソッドです。体幹を強化することで姿勢改善や柔軟性向上が期待でき、腰痛や肩こり、筋肉の疲労を予防します。特に、体力に自信がない人でも無理なく取り組めます。ピラティス特有の呼吸法を通じて心身のリフレッシュやストレス軽減にもつながります。
ピラティスの効果
- 加齢による筋力低下や判断力低下を防ぐ
- バランス感覚を向上させ、転倒リスクを軽減
- シニア社員や肉体労働者にとっての健康を維持
実際に、ピラティスは、海外で幅広い層に選ばれる運動法として、その人気を確立しています。その理由は、体幹強化による姿勢改善や柔軟性向上、そして全身のバランス調整にあります。特にデスクワーカーやアスリート、高齢者までが取り入れやすく、長く続けられる点で評価されています。
他の健康法と比較
ピラティストの比較で、ヨガやラジオ体操があげられますす。
- ヨガは柔軟性を高め、体のバランスを改善することに役立ちます。ピラティスはそれに加えて、体の安定性を強化する点で優れています。ピラティスの動作は、コアを意識して動くことで体のバランスを整え、身体の深層筋を鍛えることができます。これにより、転倒や怪我のリスクを軽減する効果が期待できます。
- ラジオ体操では、日常的なバランス能力や安定性の強化には限界があり、ピラティスのように安定した身体を作る効果はあまり期待できません。(加えて、朝しかできません)
特にシニア社員にとっては重要な健康維持法です。
ところで、肩こりや腰痛でマッサージに通っても、すぐに不調が戻ることはありませんか?
その原因は、体幹の弱さにあることが多いです。マッサージは一時的な緩和には効果的ですが、根本的な改善にはつながりません。
そこでピラティスが有効です。
ピラティスは体幹を強化し、姿勢改善やバランスの安定を促す運動です。これにより、肩や腰にかかる負担を減らし、慢性的な不調を防ぐことができます。また、呼吸法を取り入れることで心身をリフレッシュし、ストレス軽減にも役立ちます。
ピラティスを続けることで、マッサージに頼らなくても根本から健康を保つことができるのです。
ピラティスの課題
ピラティスの課題としてよく挙げられるのは、専用の設備や指導者の不足です。ピラティスは正しいフォームや呼吸法が重要なため、専門的な指導が必要で、特に初心者にとってはジムやスタジオの設備が求められることが多いです。
しかし、この問題はすでに解決されています。
筆者は、ピラティスの指導実績や豊富な知識、設備、そして広い人脈を備えています。これまで多くの方々に対してピラティスの効果を実感していただき、数々の成功事例を持っています。さらに、オンラインとオフラインの両方で指導が可能な設備を完備しており、専門的なトレーニングを提供できる環境が整っています。
また、業界内での幅広い人脈を活かし、質の高い指導者との連携を通じて、初心者から上級者まで、あらゆるレベルに応じたトレーニングが可能です。このように、ピラティスに関する全てのリソースを揃えており、皆様に最適な健康サポートを提供いたします。
3.ピラティスを始めるタイミングは?
さて、ここでピラティスを導入することの重要性についてお伝えしたいところですが、あえてここで「待った」をかけさせていただきます。実は、私たちが本当に目指しているのは、単にピラティスを始めてもらうだけでなく、経営課題に本気で応える形で導入することです。
そのため、すぐに始めるのではなく、まずは2〜3カ月かけての打ち合わせや体験レッスンを通して、現状の課題を深くヒアリングし、ピラティスがどのように効果を発揮するかを事前にご理解・共有いただきたいと考えています。
この取り組みは、単なる一時的な施策ではなく、長期的な視点で経営に適応できる形で提供するものです。貴社の経営課題を根本から解決するための真剣なパートナーとして、ご一緒させていただきたいと考えています。
ピラティス導入前にヒアリングすべき項目を、男女比やコミュニケーション頻度、社員の国籍、食事、勤務時間なども含めて再構成しました。これにより、より包括的な理解が得られ、企業や社員の状況に適したプログラムを提供できます。
これらのヒアリング項目を基に、社員の健康状態や働き方、文化的背景に合った最適なピラティスプログラムを提案していく所存です。なぜなら、先ほど申し上げたように、経営陣は今後のシニア人材の健康を支える義務を背負う!とお伝えしたように、私たちもその義務を一緒に背負う覚悟だからです。
よって、導入プロセスから、ピラティスが社員の健康だけでなく、組織全体のパフォーマンス向上にどのように貢献するかを実感できるよう尽力していきます。
4.最後に...今後の人材育成
スキルは時間とともに成長しますが、健康はその逆です。時間とともに衰えていきます。だからこそ、従業員の健康を第一に育んでいくことが最大の人材育成なのです。

実は、この考え方は、私が駆け出し時代にお世話になった社長からの受け売りです。
その方は、大病を経験し、健康の大切さを身をもって学びました。だからこそ、社員には長く健康でいてほしいという強い思いから、何度も議論を重ね、会社に最適な健康管理の取り組みを導入していきました。
その社長とは、気がつけば20年以上の付き合いです。正直、私自身もハードなスケジュールで体を壊しそうになったこともありましたが、それが後任の育成に踏み切るきっかけとなりました。
人との出会いが人生を変えるなら、毎日健康でいることが、その出会いを生かす第一歩です。健康であるからこそ、素晴らしい縁を大切にし、会社も社員も、さらに成長し続けることができるのだと私は信じています。
Pilates For Everyone!
ピライティスの発展に貢献します。ピライティスのトレーナー様、これからピライティスを始めたい方へ

ピラティスかけこみ寺
ピライティストレーナーの相談窓口です

ピラティスのお申込み
Studio P-bodyの公式ホームページ